【本屋で本を書く】月岡ツキ『傷つきながら泳いでく』書き下ろしエッセイ
2026-01-16
2025-07-18
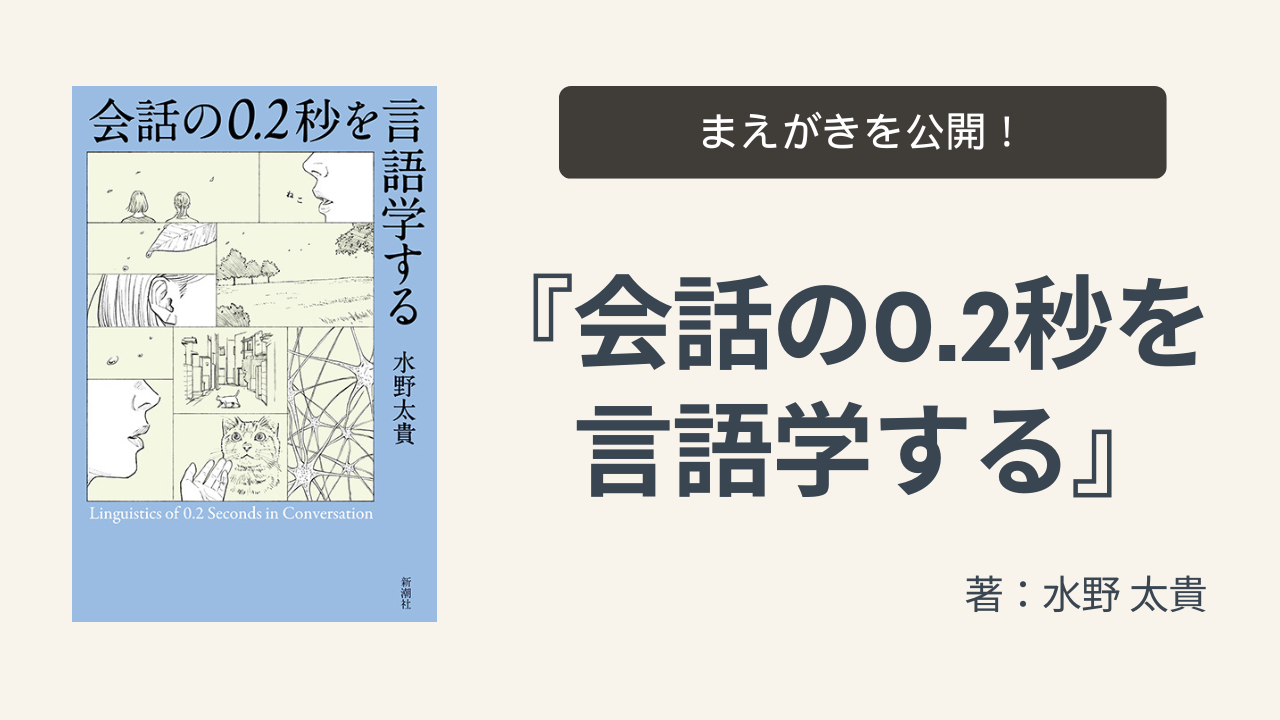
2009年8月、ドイツ・ベルリン。アメリカの陸上選手であるタイソン・ゲイは唇を嚙んだ。世界陸上の男子100メートル走決勝、彼が出したタイムは9・71秒。銀メダルだった。表彰台の横に立つのはジャマイカのウサイン・ボルト。今も破られぬ9・58秒という世界新記録を叩き出した男だ。その差はわずか130ミリ秒。
この130ミリ秒──つまり0・13秒という数字をあなたはどう思うだろうか。きっと、極めて短い時間だと感じる人が多いだろう。
しかし見方を変えると、あなたも毎日のように、1秒以下のわずかな時間で競争を繰り広げている。それが、会話だ。
会話では、一人の話者が話し、それが終わると別の人が話し始める。話者が交替するまでの発話を「ターン」といい、話者の交替を「ターンテイキング」というが、イギリスの言語学者であるスティーヴン・C・レヴィンソンらの研究によると、ターンテイキングには平均して200ミリ秒──つまり0・2秒しかかからないという¹。タイソン・ゲイが涙を呑んだ130ミリ秒とさほど変わらない、極めて短い時間である。
別の研究では、10の言語で「はい/いいえ」で答えられる質問文を与え、応答に要する時間を調べた。各言語の所要時間の中央値は0ミリ秒から300ミリ秒だったそうだ²。やはり1秒どころか、500ミリ秒もかかっていない。僕たちは会話において、100ミリ秒単位の世界で高度な駆け引きを行なっているのである。
この事実に対する反応は、大きく分けて二つだろう。僕はたまげた。そんなに短時間で応答できるなんてすごすぎる。だって、応答するためには、相手が言っていることがわからなければならないわけだ。その上で、何を言うかもまとめておく必要がある。もう一度言おう。この間、たった200ミリ秒だ。すさまじい高速処理だと驚くのが一つ目の反応である。
一方で、「まあ、そんなもんだよね」と受け流す人も少なからずいるのではなかろうか。何しろ、あなたも毎日やっているのだ。
「一度読んだ文書はどんなものでも諳んじることができる³」と聞けば、誰でもすごいと思うはずだ。これは言語学者ジョン・ライデンのエピソードだが、疑う余地のないほど超人的な技能である。こうした特殊な能力なら、評価が割れることはない(ただ、ライデン自身はこの能力に不便を感じていたようである。なぜなら、一つの箇所を探し出すには、文書全体を冒頭から暗唱しなければならなかったからだ)。
一方、日々観察でき、自分自身でも行なっているターンテイキングを改めて評価されても、何がすごいのかピンと来ない人もいると思う。このすれ違いの原因はシンプルだ。あなたは相手の発言を理解したり、あるいは自分で文を作ったりすることの大変さを知らないからだ。後ほどじっくり説明するが、これはきわめて高度な処理が行なわれている。一時期、人間の言語を動物にも教えようとする研究が流行したが、ついぞヒトの言語を使いこなす動物は現れなかった。
それから、200ミリ秒がどれほど短いのか、いまいちピンと来ていない人もいると思う。そこでもっと身近な例を挙げよう。あなたがスマートフォンで、何かのサイトにアクセスしたとする。その際、どのくらいなら待機できるだろうか。一般論として、人は400ミリ秒以上待たされると、興味を失う可能性がグッと上昇すると言われる。これは「ドハティの閾値」⁴と呼ばれ、ウェブサイトやアプリの開発をする人にとっては死活問題とされる。
しかし会話研究の視点からドハティの閾値を見ると、まだまだ悠長だともいえる。ヒトはターンテイキングにおいて、400ミリ秒も待ってないからだ。
ヒトはわずか200ミリ秒でターンテイキングをしている。この事実を知ってから、僕は友達と会話する際も、応答までの間にどうしても注意が行くようになってしまった。そのせいで会話自体に集中できなくなったこともある。その功罪はさておき、どうやらこの事実に心を奪われてしまったようなのだ。かくして僕は、この魅力的な問題についてリサーチを始めることにした。
ところが意外なことに、この問題について簡潔に、そして包括的にまとまっている本が見つからない。最も関係しているのは言語学だろうとは思っていたが、調べていくとどうやらそうとも限らないらしい。始めた当初はまったく予想もしていなかったが、結局、社会学や哲学、文化人類学などの文献にも目を通した。
せっかくなので、このリサーチの結果を皆さんに楽しくシェアしたい。これが本書のコンセプトだ。本書は僕自身が調べながら、1章ずつ書いていったので、読みながら調査の過程を追体験できるようになっている。それから、後ほど詳しく説明するが、僕自身は研究者でも何でもなく、あくまで一人の言語学好きだ。学術論文の知見などを反映した内容にはなっているが、高校生だったころの僕でも読めるように書いたので、ぜひ気負わずに読み進めてほしい。
ということで、本書が扱う中心的な問いを改めて確認しよう。
「ヒトがわずか200ミリ秒でターンテイキングを行なうには、言語にまつわるどのような知識が頭の中に必要で、具体的にはどんな処理が必要か?」
これを「200ミリ秒の謎」と呼び、以降の章で取り扱いたい。
改めて見ると、たった200ミリ秒間の出来事だけで、何をそんなに書くことがあるのかと思えてくる。僕だってリサーチを始めるまでは、うっすらそう思っていた。
しかし、過去にはこんな本もある。『ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い10分間の大激論の謎⁵』というノンフィクションだ。1946年10月25日、イギリスの哲学者カール・ポパーとオーストリア生まれの哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインはケンブリッジ大学で初めて顔を合わせた。ウィトゲンシュタインが議長を務める定例の討論会に、ポパーが招待されたのだ。そこで「哲学が扱うべき問題とは何か」という議論が白熱しすぎて、ウィトゲンシュタインは興奮のあまり火かき棒を振り回したという⁶。白熱しすぎである。
ともあれ、この本はたった10分間の激論の全貌を解説すべく、そこに至るまでの背景や真相の解明を464ページかけて解説している。であれば、200ミリ秒の謎に240ページを費やしたってなんらおかしくない。
なぜ僕が200ミリ秒の謎にそこまで魅せられているのか、少しだけ補足したい。ここからは取るに足らない自分語りなので、興味のない方は第一章まで読み飛ばしてもらってOKだ。
僕は一介の言語好きだ。
そのきっかけは小学2年生のときで、難読漢字にハマり、学校の漢字ドリルそっちのけで、画数の多い字をノートに書いて先生に見せていた。僕にとっては、ドリルの漢字があまりに簡単で退屈だったのでやっていただけだったのだが、先生は褒めてくれた。その結果どんどんエスカレートし、小学5年生のときには難読漢字に関する自由研究をノート8冊にまとめて提出する。先生には一通り褒められたあと、心配された。
それから、当時はやることがないと国語辞典を読んでいた。親が「夏休みは1日1時間は勉強しなさい」と言うのだが、僕は勉強が嫌いだった。でも、辞書を読んでいる時間も勉強にカウントしていいと言う。ちょっとした反抗のつもりで読み始めたら、どんどん知らないことばが頭に入っていく。小学生にしては異常なボキャブラリーと漢字力を獲得した僕の当時の趣味は、テストの解答の中に難読漢字を多く盛り込むことだった。一回、国語の試験で解答欄に「雪隠(せっちん。トイレのこと)」と書いたら、先生に「読めない」と採点してもらえなかった苦い過去がある。
漢字は中1のときに漢検二級をとってから、しばらくのあいだ飽きてしまった。しかし高校に入ると、今度は英語にハマった。現代英語の文法には、理不尽がいっぱいある。なぜ冠詞には a と an があるのか。なぜ過去形には不規則活用があるのか。なぜ night は綴り通りに読まないのか。なぜ仮定法だと I were となるのか。よくわからないのだが、とりあえず覚える。
ところがある日、実はそこに理由があったことを知る。例えば冠詞の a/an は、もとをたどると one と源を同じくする。だから単数名詞につくわけだ。そして one と形が似ているのは an だ。そう、英語の不定冠詞はもともと an が主流だったのだ。歴史的に見れば a のほうが後発で、そしてイレギュラーな存在なのである⁷。
余談だが、この a/an の共存のせいで巻き添えを食らった気の毒な単語がいくつもある。例えばエプロン(apron)は、もともとネプロン(napron)だった。ところが a napron という形を見た人々が、an apron と切れるのではと誤解した。その結果、現代では napron という語形は忘れ去られ、もっぱら apron が覇権を握るようになったのだ。こうした現象を異分析といい、ほかにもニックネーム(a nickname)ももともとはイックネーム(an ickname)だったと考えられている。
こんな調子で、英文法の疑問には大体理由があることを知ると、学校で習ったことすべてについて深掘りしたくなってくる。こうして高校時代の僕は青春を犠牲にして、英語について調べる日々を送っていた。
進路選択は迷わなかった。僕は高校のテスト週間になると地元の図書館のことばコーナーをハンターのような目つきでうろつく習慣があり、そこで言語学という学問分野があることを知っていたからだ。また、近所の名古屋大学文学部には、著書をいくつも読んでいて、テレビで見たことのある町田健先生もいる。迷わず言語学研究室のドアを叩いた。
ここまでは順風満帆なのだが、大学時代は友達と遊ぶことに夢中で、さっぱり勉強しなかった。大学院への進学をまったく検討することなく就職活動をしたのだが、そこでも漠然と「ことばを扱える仕事がいい」とは思っていた。運よく出版社が拾ってくれたので、ありがたいことに、今は編集者として毎日のようにことばと向き合っている。
記事タイトルをつけるとき、「キーマンを直撃!」と「キーマンに直撃!」はどちらがいいだろうか。そもそもこの二つはどう違うのだろうか。こんなことを、お給料をもらいながら考えられるのはとても楽しい。
ことば漬けの時間は、本業だけでなくプライベートも侵食し始めた。というのも僕は今、「ゆる言語学ラジオ」という YouTube、Podcast(インターネットを通じて配信される音声コンテンツ)番組をやっているからだ。これは作家の堀元見さんに誘ってもらって2021年に始めたインターネットラジオで、言語学に関するトピックを中心に扱うゆる~い番組だ。現在 YouTube 登録者数は36万人(2025年7月6日時点)で、多くの方に聞いてもらっている。
おかげさまで、朝から晩まで、平日から土日まで、ことばのことで頭がいっぱいだ。ことば関係の蔵書だけで、家の本棚は二つ埋まっている。
ありがたいことに「ゆる言語学ラジオ」では、話のスキルを褒めていただけることがある。しょっちゅう「テンポがいい」と言われるのだが、実際に僕たちの会話のテンポはものすごく速い。何かを問われて沈思黙考することはほとんどないし、言いよどみやつっかえも少なくて、いつもスラスラ話している。相方はどうか知らないが、僕なんかはプライベートで人と会うときにも幾度となく「会話が速い」と言われてきた。
そんなわけで、僕は「ことば」と「会話」を仕事にしている。そして普段からテンポが速いこともあって、200ミリ秒の謎というのは個人的な関心にもマッチしたのだった。
そろそろ本題に入ろう。コミュニケーションにおいて、発話された文はしばしば解釈が割れる。
例えばある芸能人が亡くなった際、ある YouTuber が動画内で「あの人のこと、誰も悪く言わないんだよねー」としみじみと語った。ところがそのコメント欄には、「あなたがそんな人だとは思わなかった」と憤りを表明する人が現れたという。どうやらその人は、先の発言を「もっと悪く言う人がいてもいいのに」という非難だと感じたようなのだ。真意としては、単に「それほどまでに、その芸能人はいい人だった」と言いたかっただけなのに。
このように、しばしば僕たちは一つの文に対して、異なる解釈を与えてしまう。文とは、文脈によって異なるニュアンスを持ってしまうのである。どうしてこんな悲劇が起きてしまうのだろう?
200ミリ秒の謎を解き明かす第一歩として、まずは「文脈」という厄介者と向かい合うことから始めよう。
posted by 飯田 光平
株式会社バリューブックス所属。編集者。神奈川県藤沢市生まれ。書店員をしたり、本のある空間をつくったり、本を編集したりしてきました。
BACK NUMBER